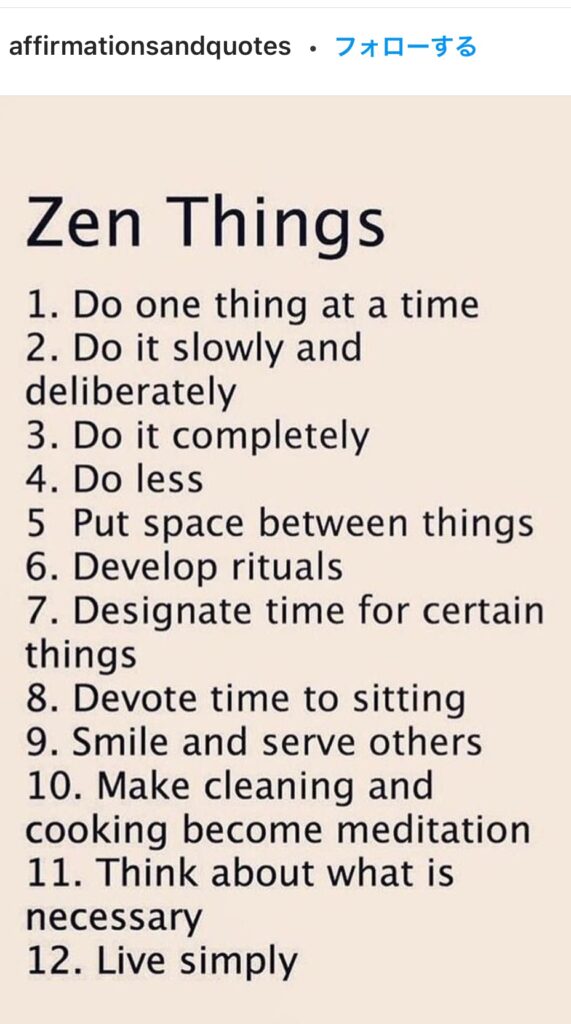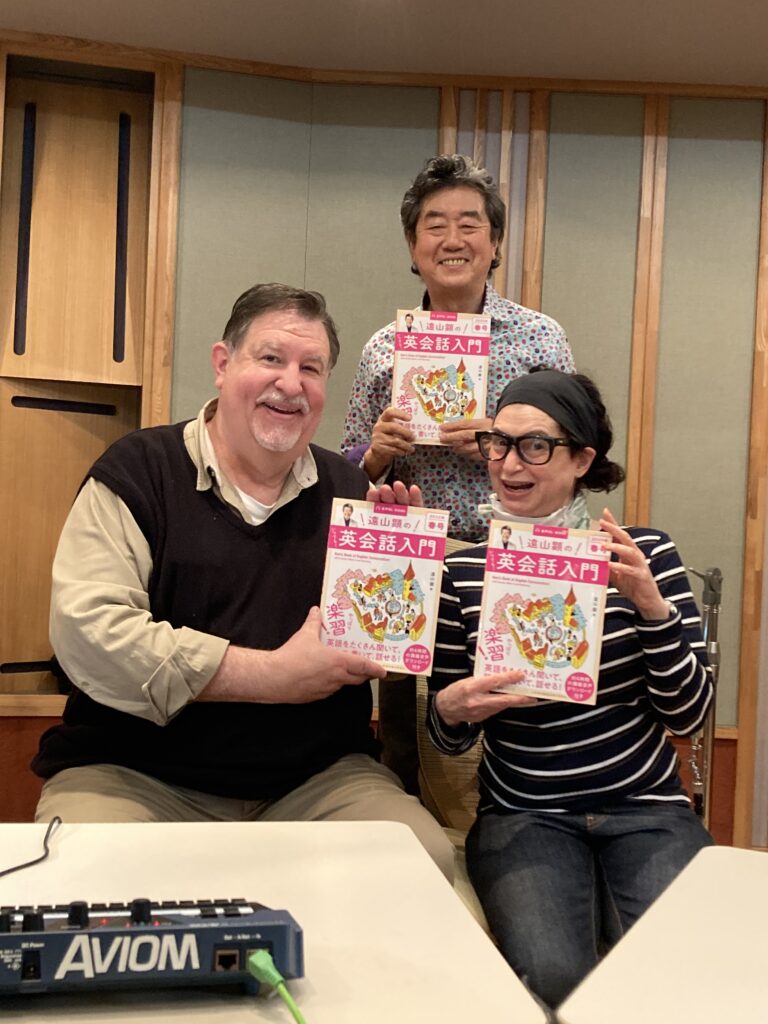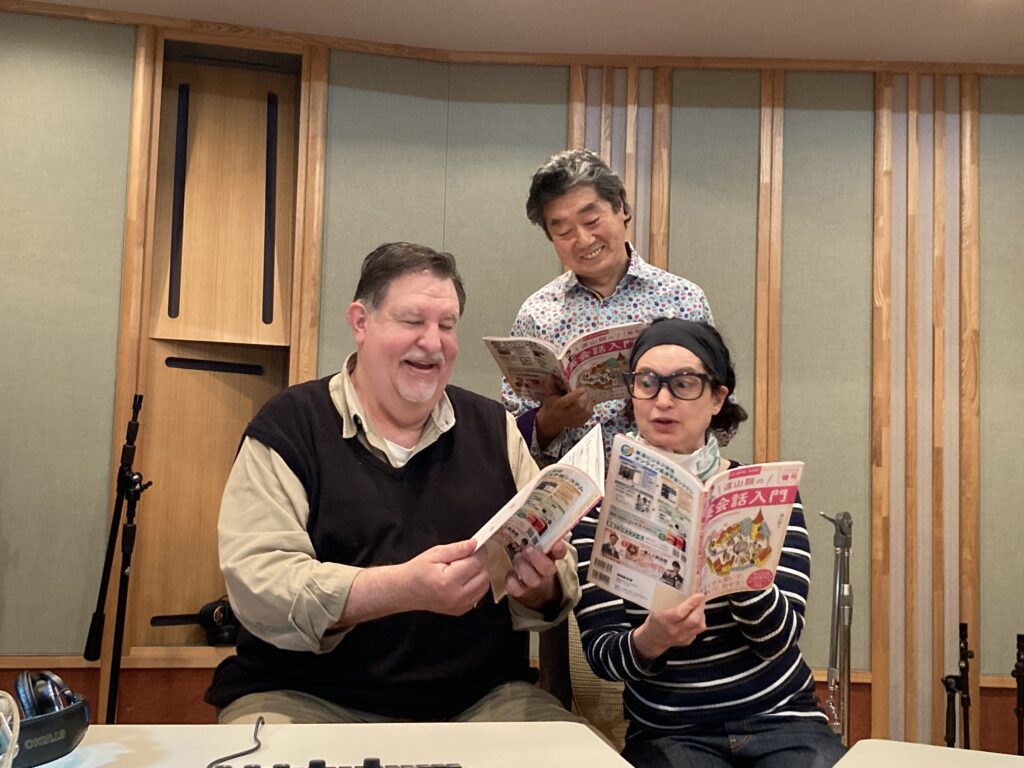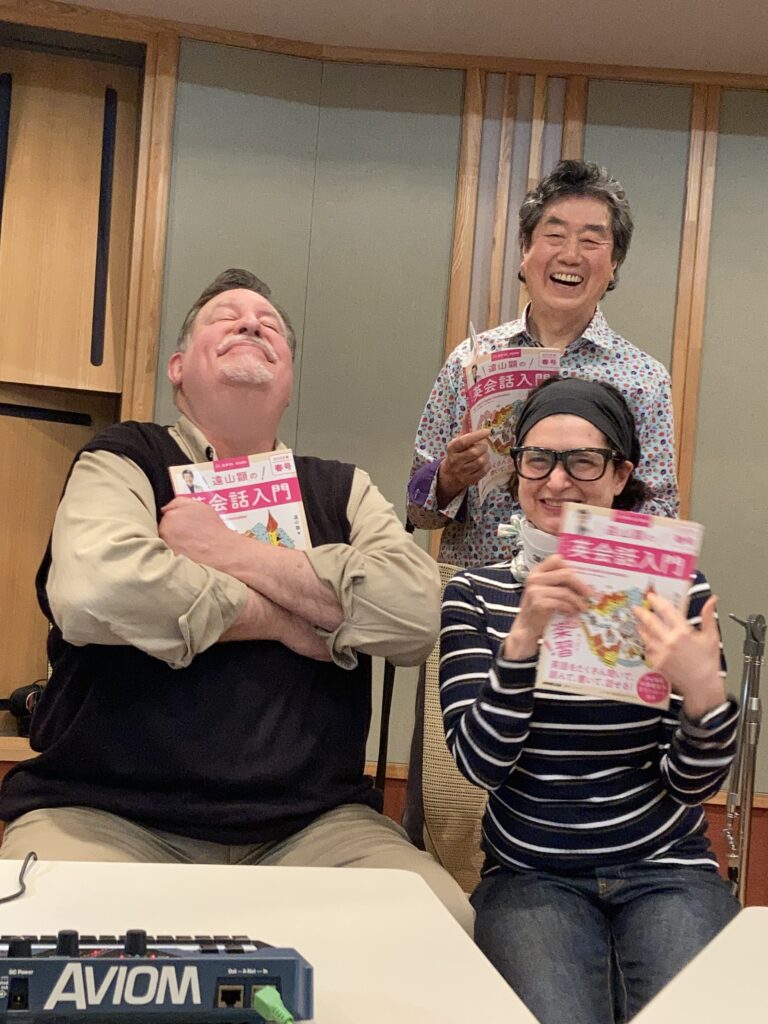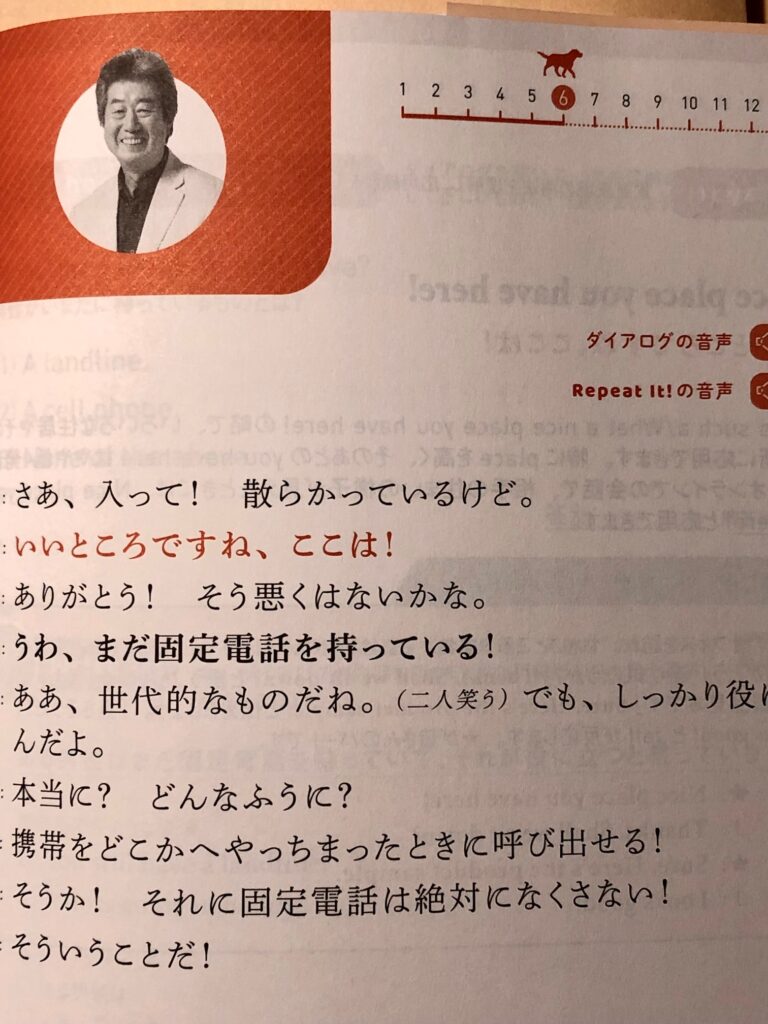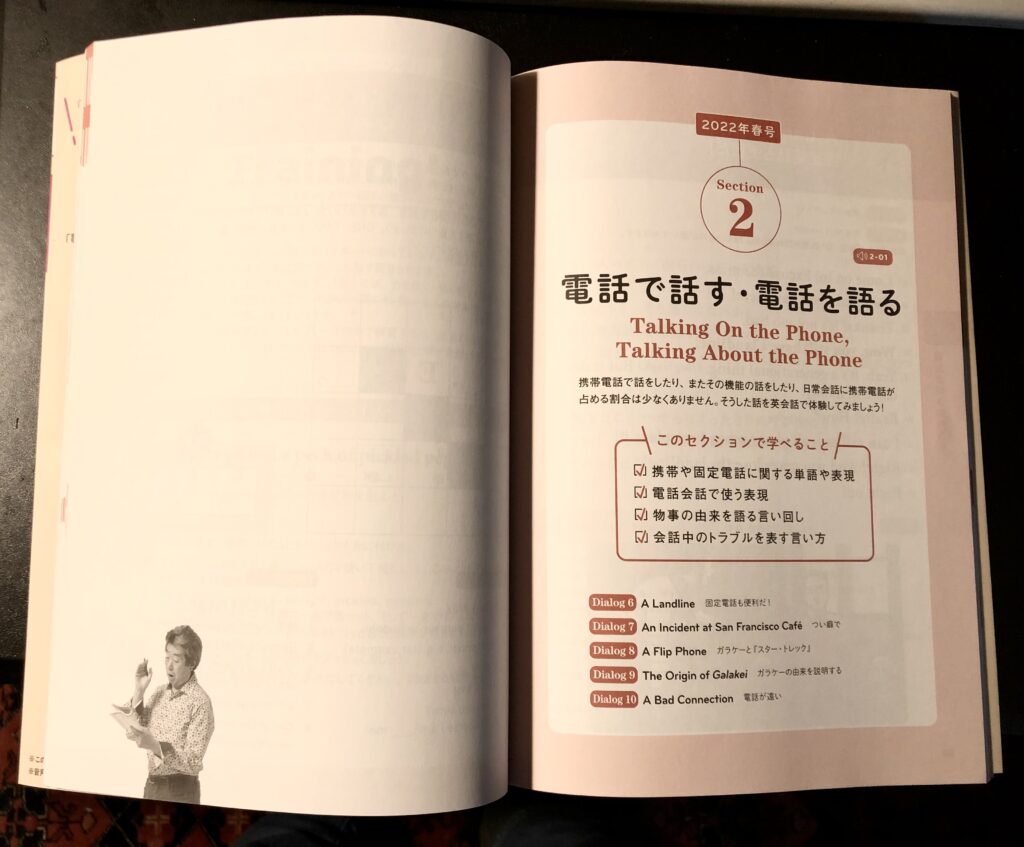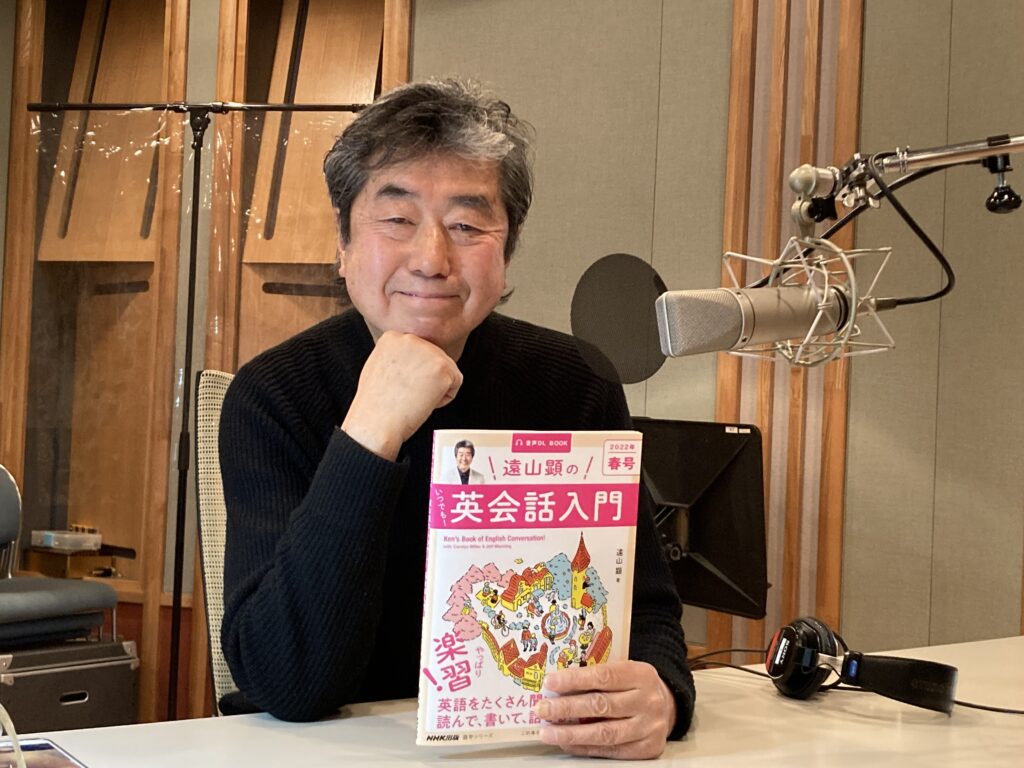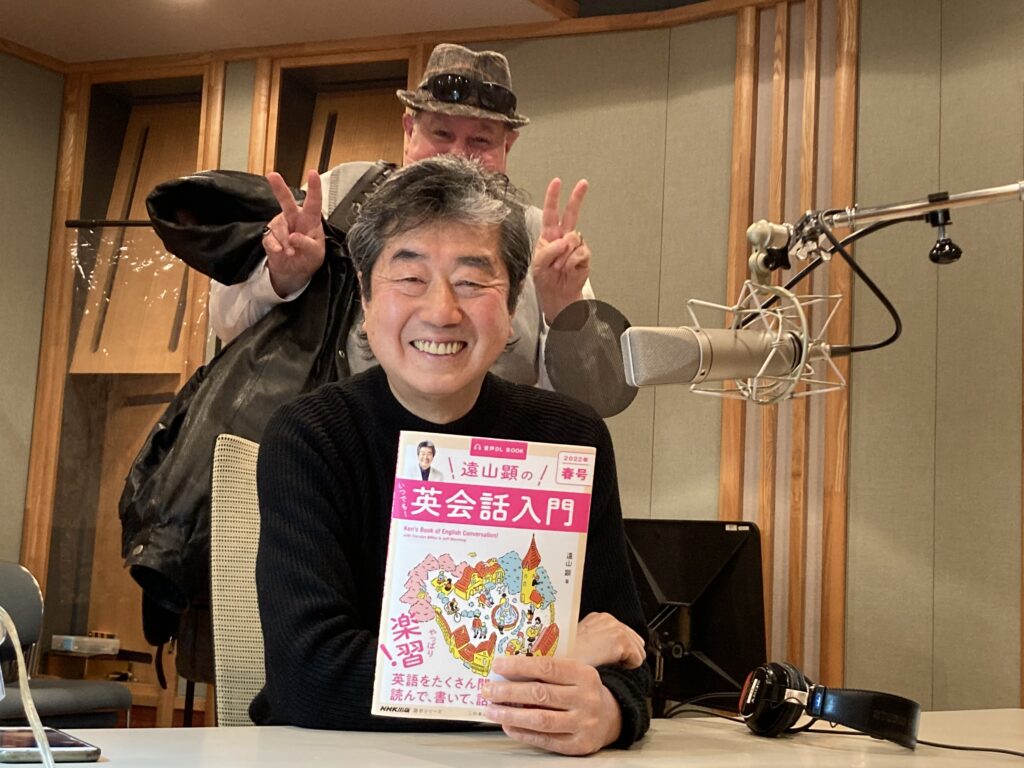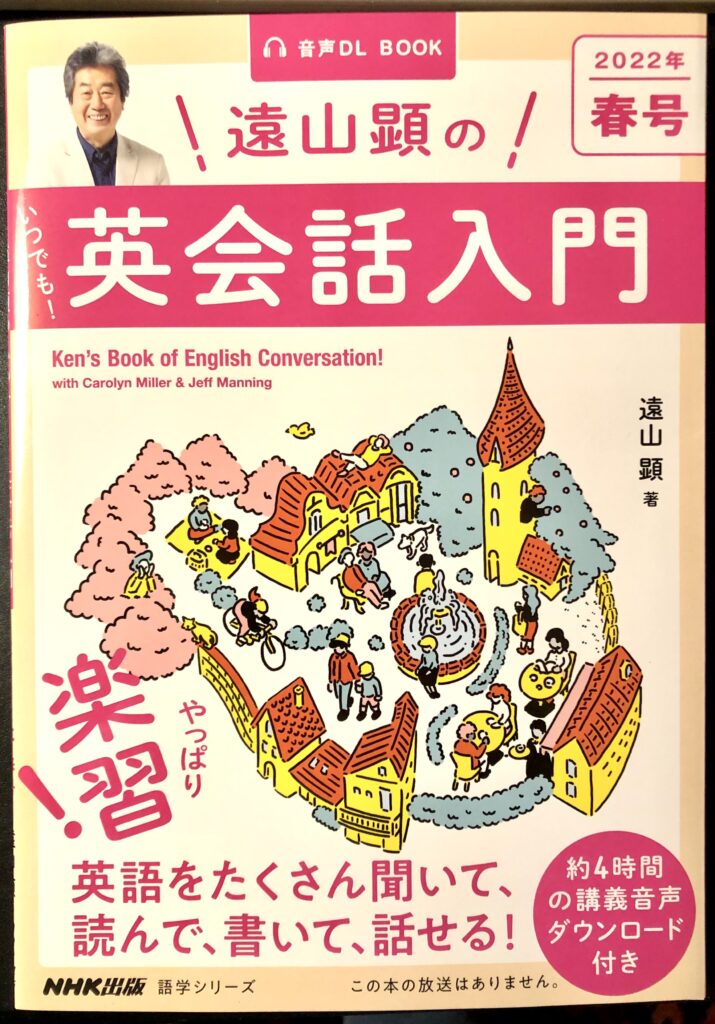英会話入門 四半世紀前のことですが あっと言う間。
つい昨日のよう もとい 明日 もとい つい明明後日のようです

ちなみ情報 「あっと言う間」
英語へ直訳: before you can say “At.” かな?
元々英語: before you can say “Jack Robinson”/”knife”
例(Free Dictionary): I’ll have the files done before you can say “knife.”
遠山応用例: Time passes before you can say “Wait.”
昨日放送されたという予告編へのリンクが送られて来ました。Many thanks!: https://twitter.com/i/status/1504598540013690883
では明日 でなく 明明後日。少し待ち疲れてしまい・・・・・